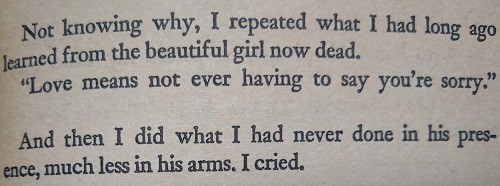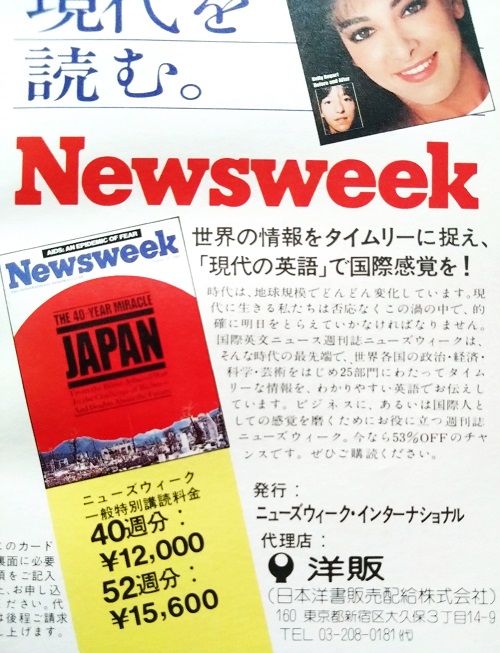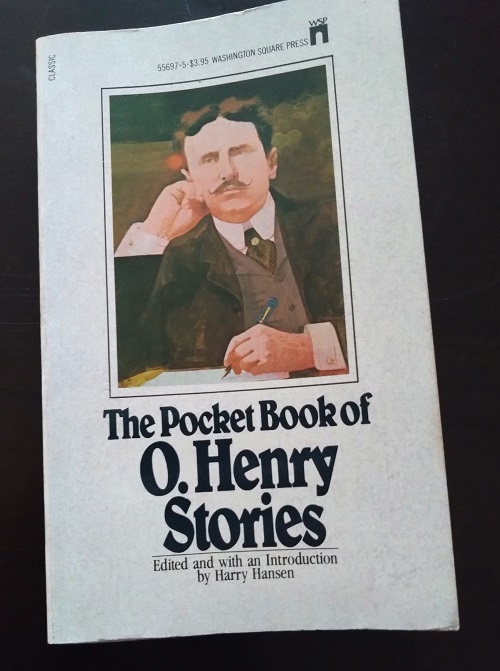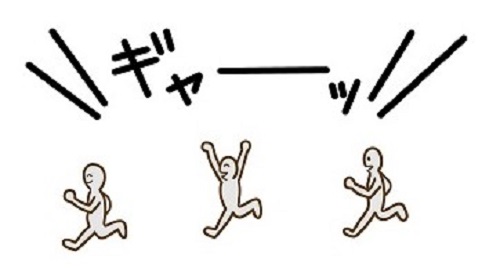能登半島地震から三週間。
被災された方々にお見舞い申し上げます。
併せて一日も早い復興をお祈りします。
おせちの蒲鉾
今年は中途半端になったおせち。
その、おせちに欠かせないのが紅白の蒲鉾です。

小田原 鈴廣の紅白の蒲鉾と伊達巻
蒲鉾の形が「日の出」に似ていることから、目出度い「初日の出」の象徴として紅白の蒲鉾がおせちに使用されているとのこと。

紅白の蒲鉾(写真AC)
薄紅色の部分は「めでたさ」や「魔除け」の意味があり、白色の部分には「神聖さ」や「清浄」の意味が込められているそうです。
全国的に珍しい金沢市の紅白の鏡餅。その由来には諸説ありますが応用できるかも…。
hanspotter.hatenablog.com
金沢の蒲鉾
と、また話が逸れかかったので舵を元の方向へ戻します。
板に乗った蒲鉾
実は、大学で上京するまで板に乗った蒲鉾を知りませんでした(と、ずっと思いこんでいました)。

板に乗った蒲鉾(写真AC)
板に乗っていない蒲鉾
金沢では、蒲鉾は板が付いていない、巻いた蒲鉾が一般的だと思います。
お隣、富山県の昆布巻かまぼこ、赤巻かまぼこがルーツでしょう。

板に乗っていない富山のかまぼこ(出典:下記の梅かまWEBサイト)
大臣賞受賞 富山かまぼこの代表格「赤巻」「昆布巻」|梅かまブログ
富山県(射水市在住)の知人からいただいた かまぼこ。赤巻と昆布巻かまぼこの包装に「越中巻」の文字があります。
金沢の蒲鉾は、富山のかまぼこがルーツだと確信しました。

新湊かまぼこ
富山の かまぼこ
富山のかまぼこが板に乗っていないのは何故か。
富山の昆布文化
富山は昆布の消費量が多い県です。
江戸時代に北前船の中継地であった富山には、北海道から昆布が運ばれ、その昆布を使った食文化が発達しました。
下記のサイトに富山のかまぼこについて載っています。
”富山のかまぼこ職人たちは、板の代わりに身近に豊富にある昆布を利用したのです!
柔らかいすり身を形作る時に昆布に巻いて成型した方が作業しやすい。
蒸したり、かまぼこを移動する時にも昆布に巻いてあった方が移動しやすい。
そして、ぐるぐる巻くことにより昆布の旨味が均等にかまぼこへ行き渡る!
(出典:河内屋ブログ)”
www.kamaboko.co.jp
農林水産省「うちの郷土料理~次世代に伝えたい大切な味~」
農林水産省のWEBサイト「うちの郷土料理~次世代に伝えたい大切な味~」で、全国の都道府県の郷土料理を紹介しています。
www.maff.go.jp
そのサイトの富山県の郷土料理の中に、
ふんわりと、とろろ昆布を纏った「とろろ昆布のおにぎり」、

黒とろろ昆布のおにぎり(出典:農林水産省の上記Webサイト)
刺身でも食べられるような新鮮な魚を昆布で巻いた「昆布〆」、

昆布〆(写真AC)
これも北海道から運ばれた身欠きニシンを昆布で巻いた「昆布巻き」、

昆布巻き(出典:農林水産省の上記Webサイト)
と、昆布を利用した料理が掲載されています。
「昆布巻かまぼこ」の発想は「昆布巻き」からでしょうね。
北前船は、危険と引き換えに船主に莫大な富を齎すと同時に、昆布文化を富山に根付かせました。
(尚、写真は富山ではありません。加賀市橋立の北前船の里資料館の展示物です。)


北前船(出典:北前船の里資料館の展示物)
細工かまぼこ
話が飛びます。
富山の蒲鉾で、板のない蒲鉾以上に珍しいのは細工かまぼこでしょう。
縁起のよい鯛や鶴亀、富士山などを蒲鉾で作ったもので、結婚式の引き出物にも使われます。
富山出身の後輩の結婚式に招かれ、引き出物の中に立派な細工かまぼこがありました。

細工かまぼこ(出典:梅かまWEBサイト)
富山県民でも意外と知らない 細工かまぼこの世界|梅かま
兎に角重かった!! でも美味しかった。
一人では食べ切れないので職場でお裾分けしました。それほど大きいものです。
これを目出度さのお福分けと言うそうです。
さて、前置きが長くなりました。本題へと進めます。
5年前のブログに書きましたが、平成の大合併前の富山市辺り(旧の富山藩)を除いた富山県のほぼ全域が加賀藩でしたから、藩政時代に富山のかまぼこが金沢でも一般的になったのだと勝手に思い込んでいました。
hanspotter.hatenablog.com
ここからが泉鏡花からの宿題になります。
hanspotter.hatenablog.com
「泉鏡花 グレーテルのかまどで巡る金沢 Part Ⅲ」に登場した泉鏡花の随筆「寸情風土記」に次のような一節があることに今頃になって気付きました。
”金澤にて(中略)蒲鉾の事をはべん、はべんをふかしと言ふ。即ち紅白のはべんなり。皆板についたまゝを半月に揃へて鉢肴に裝る。(出典:泉鏡花「寸情風土記」)”
宿題① はべん
まずは方言の問題から。
”蒲鉾の事をはべん(出典:泉鏡花「寸情風土記」”
”はべん” は私の母も使っていました。
今から30年以上前の「金沢市及び其の近郊の方言集」にも載っています。

はべん(出典:「金沢市及び其の近郊の方言集」)
宿題①の答え
”はべん”。
Wikipediaに拠ると、広義では蒲鉾の仲間である ”はんぺん” は、
”漢字では「半片」か「半平」と書くが、「半弁」「鱧餅」などとあてられることもある(出典:Wikipedia)”
半片 - Wikipedia
とありますので、当時は「半弁」即ち濁音の ”はんべん” も使用されていたのでしょう。
「金沢市及び其の近郊の方言集」には、 ”はべん” の説明に ”はんべん ” と ”蒲鉾” が並記されていますが、金沢弁では、”はんべん=はんぺん ” と蒲鉾の区分が曖昧だったのではないでしょうか。
その結果、蒲鉾との区分が曖昧だった ”はんべん” が変化して ”はべん”=蒲鉾になった………かな。
宿題② ふかし
”はべんをふかしと言ふ(出典:泉鏡花「寸情風土記」”

ふかし(出典:「金沢市及び其の近郊の方言集」)
宿題①の答えのように、金沢の方言では ”はべん” =蒲鉾です。
同じ ”はべん” が二つの意味を持っている???
宿題②の答え
推測ですが、ここで登場する ”はべん” は ”はんぺん” だと思います。
「金沢市及び其の近郊の方言集」には、 ”はべん” および ”ふかし ” の両方の説明に ”はんべん ” が出てきますが、半濁音の ”ぺ” ではなく、濁音の ”べ” と表記されています。


はんべん(出典:「金沢市及び其の近郊の方言集」)
先程のWikipedia、「半弁」から濁音の ”はんべん” のパターンですね。
この ”はんべん” を ”はべん” と誤って記した可能性が…。
従って、
”はべんをふかしと言ふ(出典:泉鏡花「寸情風土記」”
という一節は、
”はんべん(=はんぺん)をふかしと言ふ”
が正しいような…。
「金沢市及び其の近郊の方言集」でも、 ”ふかし ” を白色の軽い ”はんべん ”と説明していますし。

ふかし(出典:「金沢市及び其の近郊の方言集」)
尚、金沢で言う ”ふかし” は ”はんぺん” のように茹でて作ります。蒸して作る蒲鉾との違いです。
また、”はんぺん” は四角や三角ですが、”ふかし” は円形で紅白セットが一般的です。
宿題③ 板についたまゝ
”板についたまゝを半月に揃へて鉢肴に裝る。(出典:泉鏡花「寸情風土記」)”
「ん?」ここまで来て最後にして最大の疑問が。
”板についたまゝ” 切り分けて鉢肴に盛る???
金沢の蒲鉾には板が付いていないのが一般的なのに、板についたまま切り分ける?
その疑問に加えて、板ごと切り分けて盛った?
富山の昆布巻かまぼこ、赤巻かまぼこが金沢で普及していたのなら、”板についたまゝ” という表現については極めて「?」ですし、百歩譲っても蒲鉾の板ごと切り分けることが可能な日本刀のような包丁があったのだろうか。
随筆は大正9年。
泉鏡花の住んでいたのは当時の金沢の繁華街、尾張町。
決して田舎で情報伝達が遅い場所ではありません。
hanspotter.hatenablog.com
ここで、遠い遠~い幼い頃の濃い霧の中の記憶を辿りました。
そう言えば、経木のような薄い板が付いた蒲鉾を板が付いたまま切り分けたものが卓袱台にあったような………。
泉鏡花からの金沢の蒲鉾に関する最後の宿題③………難問です。
宿題③の答え
泉鏡花からの宿題③の答えはネットで意外と簡単に見つかりました。
便利な世の中です。
幼いHansの記憶に残っていた ”経木のような薄い板” ではありませんでしたが、
”板についたまゝを半月に揃へて鉢肴に裝る。(出典:泉鏡花「寸情風土記」)
ことが出来る蒲鉾が現在でもありました。
ひがし茶屋街にある 押寿し体験厨房 金澤寿しさんのWEBサイトのメニューに。
kanazawasushi.com
メニューの写真の後方に該当の蒲鉾が写っています。


後方に該当の蒲鉾(出典:押寿し体験厨房 金澤寿しWEBサイト)
蒲鉾を大きく撮った写真もありました。

該当の蒲鉾(出典:押寿し体験厨房 金澤寿しWEBサイト)
幼い頃の記憶とは蒲鉾の形状は違っているような気もします。
でも、板、薄い板ごと切り分けて盛られているのは記憶と合っていますし、それ以上に泉鏡花の
”紅白のはべんなり。皆板についたまゝを半月に揃へて鉢肴に裝る。
(出典:泉鏡花「寸情風土記」)”
と合致しています。
お蔭で、泉鏡花からの宿題の答えが見つかった今日です。